ネット記事のこたつライターどもが間違ったタトゥー知識で間違ったタトゥーに関する情報を日々発信しまくっている事に危機を覚えたので、日本の魅力的なタトゥー、刺青に関する情報をここから発信していきます。
以下にものしりAIとのやり取りをまとめましたので参考にしてみてください。
※AIの回答には誤りがある場合がございますので、参考に留めて下さい。
日本には和彫り以外のタトゥーも存在していた
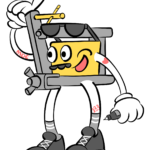
日本にはもともと和彫り以外のタトゥーも存在しましたよね?

はい、日本には和彫り以外のタトゥー文化も存在してきました。和彫りは江戸時代以降の「町人文化」と深く結びついた大きな流れですが、それ以外にもいくつかの系譜があります。
1. 古代の入れ墨(刺青)
- 縄文時代~古墳時代
考古学的な出土品や文献から、顔や体に入れ墨を施していたと考えられています。特に漁労民が「海の魔除け」として入れていたという説があります。 - 『魏志倭人伝』の記述
倭人が体に入れ墨をしていたと記録されており、これが日本最古の入れ墨文化の証拠とされています。
2. 刑罰刺青
奈良時代から江戸時代初期にかけては、犯罪者への「入墨刑」が存在しました。
- 額や腕に罪状を示す文字(犬、悪、盗など)を刻む。
- これにより、社会的烙印を押す意味を持ちました。
3. 民俗刺青(アイヌや沖縄)
- アイヌ文化の刺青
アイヌ女性が口の周りに独特の刺青を入れる習慣があり、成人儀礼・魔除け・結婚のしるしとして行われていました。 - 沖縄(琉球)のハジチ
沖縄の女性が手の甲や指に入れていた刺青。こちらも成人・結婚・魔除けの意味を持ち、明治時代に禁止されるまで続いていました。
4. 外国からの影響
- 明治以降の西洋タトゥー
日本が開国した19世紀後半には、外国人船員や旅行者が日本で刺青を入れることが流行しました。英国王エドワード7世も日本で刺青を入れた記録があります。 - 逆に日本人の中にも、海外から伝わった「洋彫り」やモチーフ(十字架、航海シンボルなど)を入れる者が現れました。
まとめ
つまり、日本のタトゥー文化は「和彫り」だけでなく、
- 古代の呪術的な入れ墨
- 刑罰としての刺青
- アイヌや琉球の民族文化
- 明治以降の西洋由来のタトゥー
といった多層的な背景を持っています。
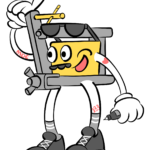
反社会的な人以外も入れたりしてましたか?

もちろんです 👍
「刺青=反社会的な人」 というイメージは、明治以降の近代社会や戦後の風潮によって強調されたもので、歴史を通じてみると 必ずしも反社会的な人だけが入れていたわけではありません。いくつか具体的に整理しますね。
1. 町人文化(江戸時代)

- 火消(消防士)
江戸の町火消は命がけの仕事でした。仲間意識や勇気の象徴として背中いっぱいに刺青(和彫り)を入れた人が多く、「刺青は勲章」と考えられていました。 - 職人・渡世人
大工、鳶、左官など肉体労働の人々が、自らの気概や美意識を示すために入れていました。夏に半纏を脱いで彫り物を見せるのが粋だったそうです。
2. 民族的習俗
- アイヌ女性
口の周りに入れ墨をして成人や結婚の証としました。魔除けや死後の世界での役割を意味することもあり、決して「反社会」的なものではありません。 - 沖縄(琉球)のハジチ
女性が手の甲や指に刺青を施し、成人や婚姻の儀礼に用いられました。文化的・宗教的な意味合いが強く、禁止されるまでは広く行われていました。
3. 権力者・外国人も
- 明治期の西洋人ブーム
日本の刺青師(彫師)は技術の高さで有名になり、観光で来た外国人が多く入れました。イギリスの王族エドワード7世やジョージ5世も日本で刺青を入れています。 - 武士階級にも一部存在
公には好まれなかったものの、一部の武士や豪商が趣味として小さな刺青を隠し入れていた記録もあります。
4. 近代以降の変化
明治政府は「野蛮」と見なして刺青を禁止したため、地下化し「反社会的」というイメージが強まっていきました。戦後も暴力団のシンボルになったことでさらにその印象が固定化しましたが、歴史的には 「勇気」「美意識」「通過儀礼」「信仰」 といった肯定的な側面も多くありました。
✅ まとめると:
反社会的な人だけでなく、火消や職人、女性の通過儀礼、外国人王族など、社会の中で尊敬や文化の象徴として刺青を入れた人は多く存在した ということです。
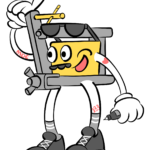
要するに近年の日本のタトゥーアンチどもが騒いでいる「アンチタトゥーは日本の文化だから」とかいう狂言は、明治以降から始まったという事です。
それまでの日本ではタトゥーは様々な人間に親しまれ好まれていたというわけです。
「タトゥーはもともと罪人うんぬん…」と良く調べもしないで言う人がいますが、それも一部の歴史だけを抜き出し他はスルーしている情弱人間の戯言なんです。














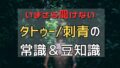


コメント